校歌をどう思う
50期 馬場 昇
標題は、私達が編集した平沼時報の特集の横見出しである。主見出しは「改正賛成が多数」、それに「三年は改正を認めず」と副見出しがついている。
私は、学校改革の初年生として新制中学から高校へと進んだ。私の家から一〇分も歩くと、中学へ行くならばあの学校へと誰もが思った神中があった。空襲で焼けた後、神中は六浦の海軍施設に仮住まいをし藤棚は復活する兆しがなかった。普通高校を選べば、新しく決められた小学区制のため岡野町に新しくできる高校に行かなければならなかった。受験した時点では学校名は決まっていなかったように思う。中学の先生は「岡野高校」となるだろうと言われた。入学金を納めたときの小さな受領書の学校名が神奈川県立横浜第一女子高等学校となっていたのが印象に残っている。近所に第一高女出身のお淑やかなご婦人がいて、「あなたがあの学校へ通うの」と言われて赤くなった。私は新しくできる高校に行くのであって女学校に行くのではないと、ずいぶん自分に言い聞かせた覚えがある。そう言われることが、屈辱であったのだ。校名の決定については後になって様々なことを知ったが、私自身が新聞部員として平沼亮三横浜市長をインタビューしたとき、「岡野さんには全く申し訳ないことになりました、私としては心苦しいのです。」と言われて吃驚したのを覚えている。帷子川に平岡橋がある。それが平沼新田と岡野新田の境で学校のあるのは岡野である。岡野氏が学校の土地を寄付しその後、県が購入した分もあるが、次々と土地を寄付され現在の敷地が出来上がったことは忘れてはならない。
さて標題の「校歌をどう思う」に戻るが、入学当初、校歌を紹介され女性合唱のハーモニーに魅せられた。しかしこれを自分たちが歌うとなると話は別である。音が高くしかも変調があって歌そのものが難しい。校歌の歌詞は、改訂されたが、いつまでも「み国の花」と歌っているのはどうなのか、蛮声を張り上げても歌える母校の校歌が欲しい、と言う声が出てくるのは当然のことで、特に快進撃する野球部の活躍を応援する男子生徒からの声が大きかった(二十七年野球部は夏の大会で準決勝まで進み、湘南高校に3−2で敗れた。湘南高校はこの時全国制覇している)。なにしろ歌えないので困った。新聞部は校歌問題に消極的な上級生部員(女性)が退部して男子部員がやっと主導権を取れるようになって、当時はやっていた世論調査形式で意識調査を行った。その結果は大部分が改正賛成に回ったが三年生は頑として改正反対を唱えた。主な主張は伝統にあった。この三年生は旧制の最後の学年であり、学校に最も長く在学したことになる生徒たちで、新任の先生は青くなるほどの強心臓の持ち主揃いで生徒総会で議論すると論調鋭くいつも物別れになった。自分たちが女学校最後の生徒と言うプライドが伝統の守り手にしたのだ。音楽の佐藤一夫先生は「作曲者は幸田延、この曲の素晴らしさが判らないか、滝廉太郎の先生だった人だ」と言われて防戦につとめた。学校側の反応はのらりくらりであった。学校は、新学制による共学を迎えるに当たり、作歌者である国文学者、万葉研究家、歌人である佐佐佐木信綱氏に、校歌改訂を依頼、完成したばかりであった。新聞はこのその後もこの調査結果を根拠に改正の方向を求めたが、実らなかった。昭和三十二年、職員会議は作詞は生徒からの公募と言う条件で新校を作ることを決め作曲を芥川也寸氏に予約するが、応募数が少なく適当なものがないと言う理由で実現されなかった。そして現在に至っている。
佐佐木信綱氏が一九一六(大正五年)十一月三日立太子礼の記念行事の一つとして校歌制定に作歌者として依頼されたのは、第一流の国文学者で歌人であり文学博士でもあったためである。この歌にふさわしい作曲家として選ばれた幸田延氏(幸田露伴の妹)は、これまた日本最初の音楽官費欧米留学生で日本に西洋音楽を輸入したといわれる。文部省音楽取調掛東京音楽学校教授で大正天皇即位の折に「大礼奉祝四部合唱曲」と言う大曲を献じている初代随一の大作曲家で、三浦環もその弟子である(中村紘子著「ピアニストという蛮族がいて」に詳しい)。こうした組み合わせで校歌ができた事は珍しいことであった。今となっては実に貴重な校歌である。 本校二回卒業生の末木美衛先生が東京音楽学校卒業後母校に勤務されたことが縁になっている。その末木先生も当時の「日本音楽年鑑」に載っている有名で立派な音楽指導者であった。七十周年の時、原稿をいただいた先生も今は亡い。
卒業後十二年で母校に奉職する機会を得て、応援団が新入生に校歌練習をさせる場面に立ち会って太鼓が入るとそれでもなかなかではないかと思うようになった。私にとって入学したときのあのたおやかな透き通った中に凛と響く女性ハーモニーも校歌であるけれども「ソレー」の掛け声がかかる応援団のエールが入り重々しくなった校歌が懐かしい。
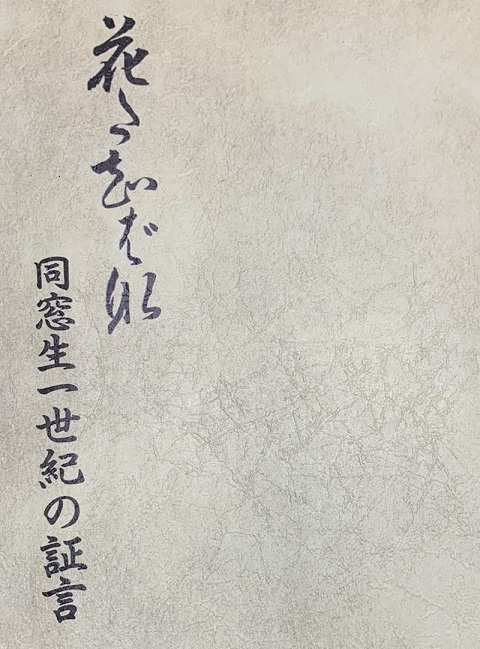

青春かながわ校歌祭にも積極的で、毎年参加してくださった馬場昇先生。(前列右から三人目)
心よりご冥福をお祈りいたします。(写真は2018年10月21日神奈川県立青少年ホールにて)





